 放熱−迷惑なその日
放熱−迷惑なその日
 放熱−迷惑なその日
放熱−迷惑なその日
|
・・・月のころ・・・ 「そぉんな顔しないのよ、ヨーコ」 つん、と佐々の額を指でつついてドライマティーニを空けながら楽しそうにアガタ 少佐=マリアンヌは言った。流し目は妙に色っぽい。ふだんはメガネと白衣で 押し隠されているとはいえ、典型的なブロンド美人である。ただし肌の色は濃く、 アングロサクソンのWASPといわれる人種ではなく、この時代ありがちな多種混 血であることを示している。薄いグリーンの瞳、ブロンド・ヘア、そして形の良い 濃い眉、抜群のプロポーション。どんな男でもその魅力の虜にしてしまいそうな そんな女だが、機械とメカが何より好きで、人間の男よりはロボットを偏愛し、 メカを愛でる。葉子からすれば一種のヘンタイである。 ――だが、そのメカ好きが嵩じての付き合い、という面もあるから、気が合わな いというばかりでもないのだ。腕は一級だし――やっぱりマッドサイエンティス トの一種だろう。人を機械と同等に扱いやがるし。だが佐々は“マッド”の付き そうな科学者連中なら見慣れていた所為もあっただろう。 それよりも、その女にはもう一つ別のやっかいな癖があった。 「相変わらず、クールな美貌よねぇ、ヨーコ」 上目遣いに見やられて、「お前に“beauty”とか言われたくないわ」と返し、 「相変わらずだな、そのタルいしゃべり方は何とかならんのか」 切り返すように冷たくあしらって、髪から頬にするりと伸びて触れてきた指を、 ふわりと跳ね除けた。 「あらん? いいじゃない、少しくらい。日本人の肌って気持ちよいのよ、キメが 細かくて」 「気色悪いこと、言うな。私は女と触れ合う趣味はない」 「まぁ、冷たい」 うふん、と笑ってマリアンヌはまたつまみに手を伸ばした。 「ここのお酒、けっこうイケるでしょ?」 葉子の方は、お洒落なカクテル方面には手をつけず、相変わらずである。モル トをロックで空けて、地味に飲んでいる。 「男らしいというか――」くすりとマリアンヌが笑う。「いかにも戦闘員って感じよ。 似合っているから良いわね」その言い方がイヤミではないのは、大和民族には 絶対に真似できない文化だと思う。 ――奥ゆかしいんだよ、私らは。てめーら狩猟民族と一緒にすんなって。 宇宙時代になって、どうもこうもないはずだが、佐々はそういった(ナンパな方面 の)意味では、典型的日本人だという自覚があった。 「バレンタイン、よねぇ」 ふぅ、と脱力したように肩を前にのめらせて、じっと見つめる目が潤んでいる。 目を伏せて酒に専念している葉子が目をやると、うふふ、とさらに笑う。 相変わらずだよな、この女。 「――あんな日本の悪しき習慣、何故世界中に広まっちまったんだか」 「そりゃね」とマリアンヌ。「チョコが嗜好の高級品になった時代があったからで しょ」 そうかもしれない、と葉子は思う。それに、なんといってもチョコレートは美味だ。 習慣として受け入れられない部分はあっても、嗜好品としては彼女だって好き なのである。だから、毎年のように(何故か)四郎と獲得数を争う程度に集まっ てしまうチョコレートも、けっこうありがたくいただいていたりもするのだ。 だがな。 それに“特別な意味”、込められましても。 はぁぁ。 「皆、狙ってる、わよ?」意味深な目をしてマリアンヌが言う。 ふう、と横向いて。「――いったい、女が女にチョコ送って何が楽しい!?」 いつも言うことだが。しかも、自分には決まった相手がいる。 「“天翔る戦女神”――貴女に憧れない女士官なんて居なくってよ?」 「……好きでやってるわけじゃねー」 「また。照れなくてもいいじゃない」 「照れてなんざ、いない。単にそういうめぐり合わせだっただけだ」 「めぐり合わせ、ねぇ…」 確かにそういうことなのだろうと、マリアンヌも思う。葉子がヤマトに乗ったの も、米国という国が一度崩壊した時、生き延びた自分がこの女性と出逢った のも。共に過ごした短い期間も。 マリアンヌの胸の裡も知らず、葉子はまた酒を口許に持っていった。 (バレンタイン・デーか…) 今年もまた、憂鬱だ。 ――なのになんたって、その火元の一つみたいな北米支部に、わざわざ自分 からやってこなきゃならない。真田や結城を恨む筋合いではないと思うのだが、 こんなタイミングで呼びつけてくれた目の前の女を恨む権利くらいは、あろうと いうものだろう。 酒が入っているし、厭な女だが昔馴染みでもある。任務その1はなかなか順 調に果たした。…少しはプライヴェートな顔も出ているのだろう。知らず表情が表 に零れていたらしい。 「ふふ」マリアンヌが笑った。「――拗ねたヨーコって、カワイイ」 「拗ねてなんか、いない」 なに言ってる。 いちいち構っていたらキリがない。 「いいえ、拗ねてる」 視線が絡まるような気がした。 それを心地よいと思ったことはないが、もう慣れた。 いや、慣れないとこの女とは付き合えないから。クールな仕事ぶりとは裏腹に、 ねっとりとした絡まるような視線。 それは、特別な興味を持った対象にのみ顕著に向けられるからだ。  佐々葉子がマリアンヌ・アガタに最初に会ったのは、思い出すのも暗いあの時代 ――最初に赴任した月基地でのことだった。 まだ若い、ブロンド美人の登場に、荒廃寸前だった月基地は色めき立ち、ただそれ が早々に壊滅した米国というエリアから亡命してきたということで、ことさら神経質 にならざるを得なかった。 月も切羽詰っていたし――葉子たちも新米で、希みは儚く、敵の科学力は圧倒的 だったから。天を覆う圧迫感は、月にいたからこそ重くのしかかり、日々 彼女たち はそれを跳ね除けながら、裡からも外からも襲い掛かる敵、そして自らとも戦わなけ ればならなかったのだ。 西暦2198年――断続的に降り続く地球への遊星爆弾の攻撃は頻度を増し、日本 列島もその被害を蒙りはじめ、人々は地下へ移っていた。 そして、ある時代には世界を支配していたはずの米合衆国は、その1000年の歴史 を閉じようとしていた。 「お呼びですか、司令」 片岡に呼び出され赴いた月基地司令室には、ひとりの異邦人が居た。窶れた面 差し。スリムといえばきこえはよいが、痩せぎす一歩手前の背ばかり高い姿に、 粗末な身なりをし、パサついた金の髪が肩にかかっていた。震えを止めるように 拳を膝に置いて椅子に背を向け座っていた女。自分より少し年上だっただろうか、 10代でも通りそうな若さで、緊張を全身から発散している。だが、敬礼し「警護と 身辺管理」を申し付けられた葉子を見上げた目の、瞳の奥の光だけが、その全身 の印象を裏切っていた。 底光りのする目。怯えた獣のような――だが、どこか強い意思の流れを感じる目。 それでも女は笑ったのだ。ニヤりと。そして、最初の科白が。 「綺麗な方ね――光栄ですわ」 するりと立ち上がり、虚栄だったのだろうがしっかりと上から見据えてくれて、握手 した手が微かに震えていたのを覚えている。 それが、米国軍科学者マリアンヌ・アガタと、佐々葉子の出会いだった。 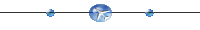 |